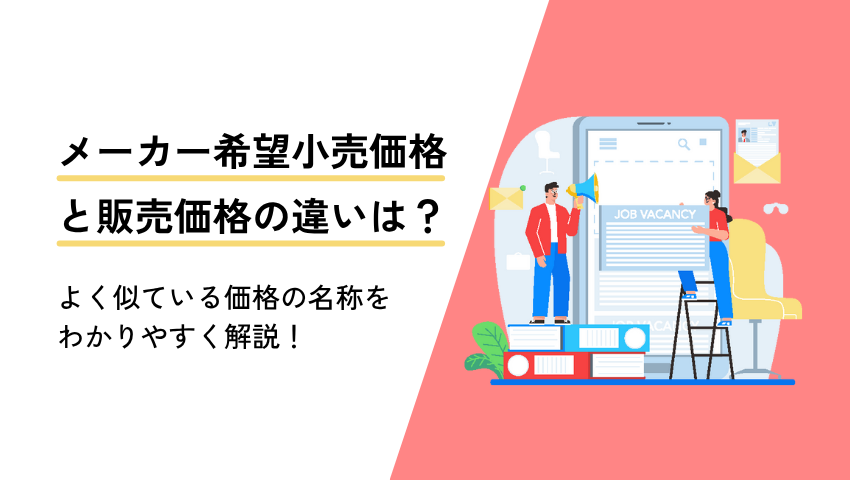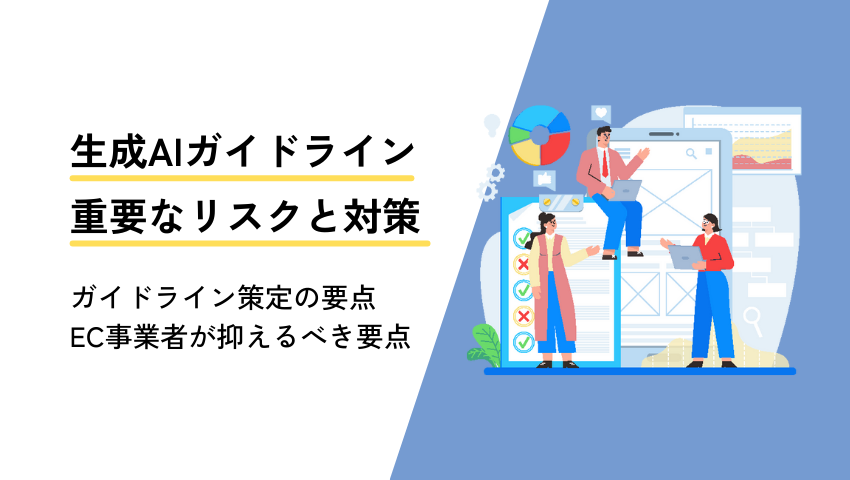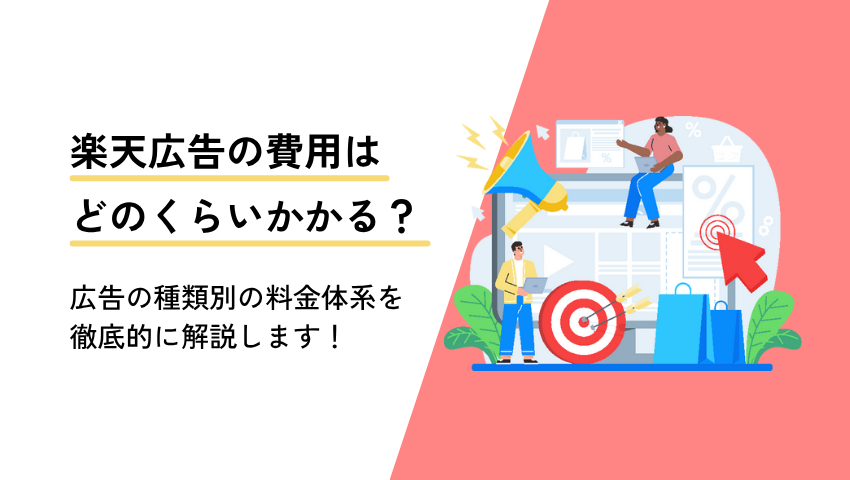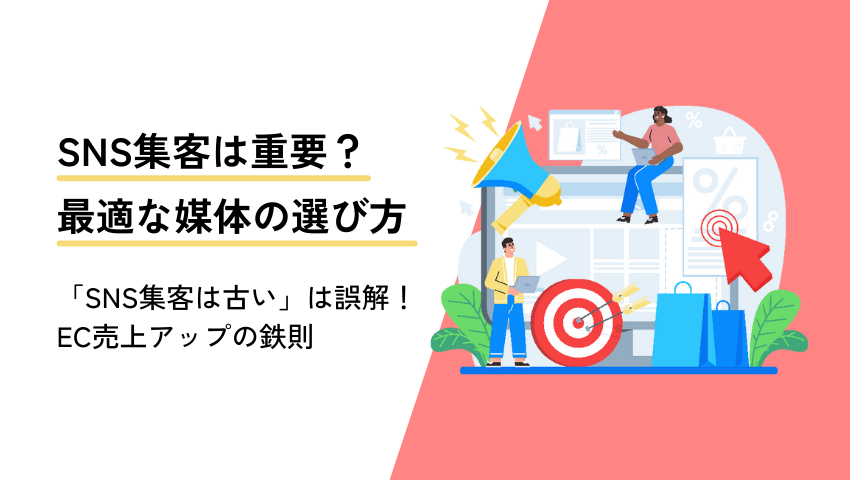キーワード一覧
キーワード検索
索引検索
さ行
-
集客
ECサイトや店舗へユーザーを誘導・動員する活動全般を指し、マーケティング用語としての正式名称は”Traffic Acquisition”などが該当します。日本語では「トラフィック獲得」と表現されることがあります。売上を作るための最初のステップであり、広告、SEO、SNSなど手段は多岐にわたります。ビジネスにおいては、単なるアクセス数稼ぎではなく、購入意欲の高い「見込み顧客」を効率的に呼び込むことが重要です。 -
ジェネレーションX
「ジェネレーションX」は、概ね1965年~1980年生まれの世代を指す言葉です。
ベビーブーマー世代とミレニアル世代の間に位置します。 青春時代にインターネットの黎明期を経験し、アナログとデジタルの両方の価値観を持つのが特徴です。2025年現在で40代半ば~60歳となり、社会の中核を担う消費の主力層として、マーケティング上重視されています。 -
サイバーセキュリティ
「サイバーセキュリティ」とは、コンピュータやネットワーク、データなどをサイバー攻撃による脅威から守るための取り組み全般を指します。
ウイルス感染や不正アクセス、情報漏洩などを防ぐ技術的な対策だけでなく、従業員の教育なども含まれます。デジタル資産が経営の根幹をなす現代において、企業の信用や事業そのものを守るための、極めて重要な経営課題の一つです。 -
サイトマップ
「サイトマップ」とは、Webサイト全体のページ構成を一覧にした「地図」です。
これには大きく2種類あります。 一つは人間(ユーザー)向けのサイト案内ページ(HTMLサイトマップ)、もう一つは検索エンジン向けのXMLファイル(XMLサイトマップ)です。前者はサイトの利便性を高め、後者は検索結果への表示を促すなどSEOにおいて重要な役割を担います。文脈によって異なる「サイトマップ」の意味
- サイトマップ(ホームページの構成図)
Webサイト全体の階層構造をツリー図などで可視化したもので、制作初期段階でページの配置を決めるために使われます。 - サイトマップページ(ユーザーに構成を伝えるページ)
上記の「ユーザー向けサイトマップ」を指し、サイト訪問者が利用するHTML形式のページです。 - サイトマップファイル(検索エンジンに構成を伝えるファイル)
上記の「検索エンジン向けサイトマップ」を指し、XML形式のファイルです。
- サイトマップ(ホームページの構成図)
-
サーバー
「サーバー」とは、PCやスマホなどの「クライアント」からの要求に応じ、データやサービスを提供するコンピュータです。
Webサイトの情報を保管し、リクエストがあるたびにWebページのデータを送り返す役割を担っています。24時間365日稼働し続ける、Webサイトや各種サービスを支える心臓部と言える存在です。サーバーが停止すると、サイトの閲覧やサービスの利用ができなくなります。 WEBサイトにアクセスをする際には、WEBサーバー(サーバーの種類)に接続して、ユーザーの端末(パソコンやスマホ)からWEBサーバーに「特定のページを開きたい」と要求(リクエスト)しています。WEBサーバー側は、その要求(リクエスト)に対して、該当のページのデータを探し出し、ユーザーの端末へ送り返(レスポンス)しています。これによって、ユーザーの端末(パソコンやスマホ)の画面に該当のページが表示されています。 -
サービス・ドミナント・ロジック
企業と顧客の取引をサービスの中心にとらえる考え方です。
2004年にアメリカのマーケティング研究者スティーブン・バーゴ氏(Stephen L. Vargo)とロバート・ラッシュ氏(Robert F. Lusch)が提唱しました。「ドミナント・ロジック」とは、直訳すると「支配的論理」です。「世界観」「価値観」といえばわかりやすいでしょう。商取引や事業活動を「何を中心としてみるか」という一種のマインドセットともいえます。
価値は企業が創り、決め、顧客に向けて一方的に送り届ける(marketing to)のではなく、顧客とともに創る(marketing with)ものととらえられます。
企業には、価値を提供することはできません。「提供する」とはつまり、企業が価値を創り、決定しているという意味を含むためです。企業にできることは、価値を提案すること(value proposition)です。結局のところ、価値を決める(創る)のは顧客ですので、企業と顧客間の相互作用(インタラクション、interaction)に重点が置かれます。 -
SimilarWeb
「SimilarWeb(シミラーウェブ)」は、競合サイトのアクセス状況を調査できるマーケティングツールです。
自社や競合のサイトURLを入力すると、全体のアクセス数や流入元(検索、SNSなど)、ユーザー層といったデータを推計値で把握できます。 競合のWeb戦略を分析し、自社の立ち位置を客観的に把握するための、強力な羅針盤として機能します。 <解析の視点>
各社間の業績の差異とウェブサイトのパフォーマンスの差異に、大きな違いがあるかを確認します。
仮に業績よりもウェブサイトのパフォーマンスが高かった場合、その企業がデジタルマーケティングに力を入れている、もしくはウェブと相性のよい製品を扱っている可能性が考えられます。逆に、業績よりもウェブサイトのパフォーマンスが低い場合は、デジタルマーケティングにあまり注力していないのかもしれません。 <ツールの使い方>
SimilarWebに対象ウェブサイトのURLを入力すると、そのウェブサイトのパフォーマンスを調査できます。
無料版の場合、URL第2階層以下を指定して調査できないため、調査対象はURL第1階層で調査できるウェブサイトに限られます。無料版は、過去3カ月間の月平均値を確認できます。ここで特に確認したい情報は、「来訪数」「平均直帰率」「平均PV」「平均滞在時間」です。 -
SaaS
"Software as a Service"の略で一般的に「サース」と呼ばれ、PC等にインストールして利用する従来のソフトウェアとは異なり、インターネット経由でサービスとして利用する提供形態を指します。
利用者は資産として「所有」するのではなく、月額料金などで必要な機能を「利用」するのが特徴です。導入や管理の手軽さから、多くの企業で活用が進んでいます。 -
JavaScript
「JavaScript」(ジャバスクリプト)は、Webサイトに動的な機能を追加するプログラミング言語です。
HTMLが「骨格」、CSSが「装飾」を担うのに対し、JavaScriptは「動き」を制御する役割を持ちます。例えば、クリックすると画像が切り替わるスライドショーや、入力内容に応じて表示が変わるメニューなどがこれにあたります。ユーザーの操作に反応する、対話的なWebサイトを構築するために不可欠な技術です。JavaScript(ジャバスクリプト)の使用例
JavaScript(ジャバスクリプト)の使用例
・画像のポップアップ表示
・Googleマップの表示
・画僧のスライド表示
その他にも、様々な専用の言語を用いることで、よりオリジナリティのあるWEB・ECサイトを構築することができます。 -
CSS
"Cascading Style Sheets"の略で、Webサイトの見た目を定義するための言語です。
HTMLがサイトの構造や文章などを決める骨格であるのに対し、CSSは文字の色や大きさ、背景、レイアウトといった装飾を担当します。両者を分離させることで、デザインの変更や修正が効率的に行えるようになります。Webサイトのブランドイメージを統一するための、いわばデザインにおける「設計図」のような存在です。CSSの使用例
【記述例】
p { <!-- HTML(エイチ ティ エム エル)タグの指定 -->
color: blue; <!-- color = プロパティ : blue = 値 -->
}
【プロパティ例】
・color ・・・・・・・・・文字色
・font size・・・・・・・・文字の大きさ
・font-family・・・・・・・文字の種類
・background-image ・・・背景画像 -
CRM
"Customer Relationship Management"の略で、日本語では「顧客関係管理」と訳されることがあります。
顧客情報を一元管理し、その関係性を深めるための経営手法や、それを実現するITシステムを指します。ECサイトでは購入履歴や問い合わせ内容を記録・分析し、個々の顧客に合ったサービス提供やメール配信に活用されます。顧客との良好な関係を築き、長期的な利益に繋げるための重要な考え方です。 -
CPC
"Cost Per Click"の略で、日本語では「クリック単価」と訳されることがあります。
Web広告が1回クリックされるごとにかかる費用を示す指標です。広告の表示回数に関わらず、ユーザーがクリックしてサイトに訪れた時点で費用が発生します。Webサイトへの集客を目的とした広告の費用対効果を測る上で、基本となる重要な指標の一つです。
CPC = 広告費用 ÷ クリック数 -
CPM
"Cost Per Mille"の略で、日本語では「インプレッション単価」と訳されることがあります。Web広告が1,000回表示されるごとにかかる費用を示す指標です。クリックや購入といった成果ではなく、広告がどれだけ多くの人の目に触れたかを測る際に用いられます。主にブランドの認知度向上を目的とした広告で活用される価格設定モデルです。
計算式:CPM=広告費用÷広告の表示回数×1000 -
CPA
"Cost Per Acquisition"などの略で、日本語では「顧客獲得単価」と訳されることがあります。
Web広告などを通じて、1件の成果を獲得するために要した費用を示す指標です。「成果」とはECサイトの商品購入や会員登録などを指します。かけた広告費を成果の件数で割って算出され、この数値が低いほど広告の費用対効果が高いと言えます。事業の採act性を測る重要なものさしであり、マーケティング戦略を練る上で欠かせない判断材料となります。
CPA(円)=広告掲載費用÷コンバージョン数 -
セッション
(session)
ウェブサイトにアクセスしたユーザーが、サイト内を閲覧し始め、離脱するまでの一連の行動です。セッション数はその数をカウントしたもので、「訪問数」「ビジット数」「訪問回数」とも呼ばれます。 -
戦略キャンバス
(strategy canvas)
2005年にフランスのビジネススクールである、INSEAD(欧州経営大学院)のるW・チャン・キム教授とレネ・モボルニュ教授が著した『ブルー・オーシャン戦略競争のない世界を創造する』の中で紹介されました。
業界における競争要因を並べ、買い手にとっての価値の高さを明らかにするチャートです。
このチャートで表す事業戦略を「価値曲線」とも呼びます。横軸には「顧客への提供価値としての業界の競争要因」、縦軸には「顧客がどの程度の価値レベルを享受しているか」(スコア)をとります。そして、高スコアであるほど、企業がその要因に力を入れていることを意味します。 -
購買調査
(ショップアロング_shop-along)
• 調査対象者の買い物に同行して普段どおりに買い物をしてもらい、その行動を観察する調査手法。
• どのように商品を選んでいるのか、どの商品と比較したのかなどを観察する。
• 買い物終了後にリサーチャーから特定の商品を選んだ理由や感じたことなどを質問して、購買行動に対する理解を深める。 -
3C分析
3C分析は、大前研一氏が1982年に英語で著した『The Mind of the Strategist』のなかで、はじめて提唱
「顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Corporation)」の3つに注目し、事業領域を分析するフレームワークです。 -
ジェネレーションZ
1997 ~ 2012年生まれ
SNSが普及していて、情報源はインターネットの動画が中心。
社会問題や多様な人材を積極的に活用する考え方の「ダイバーシティ」、障害などで排除せずに平等に仕事や学びの機会を確保する考え方の「インクルージョン」に対して関心が強い。
簡単で間がかからないことより、自分が他者と異なる個性があることを大切にしています。「デジタルネイティブ」と呼ばれ、複数のデジタルデバイス・メディアを使ってさまざまなチャネルでの接点を持っています。情報発信能力が高く、社会問題や自分の主張をオンラインやオフラインで受発信する能力に長けています。