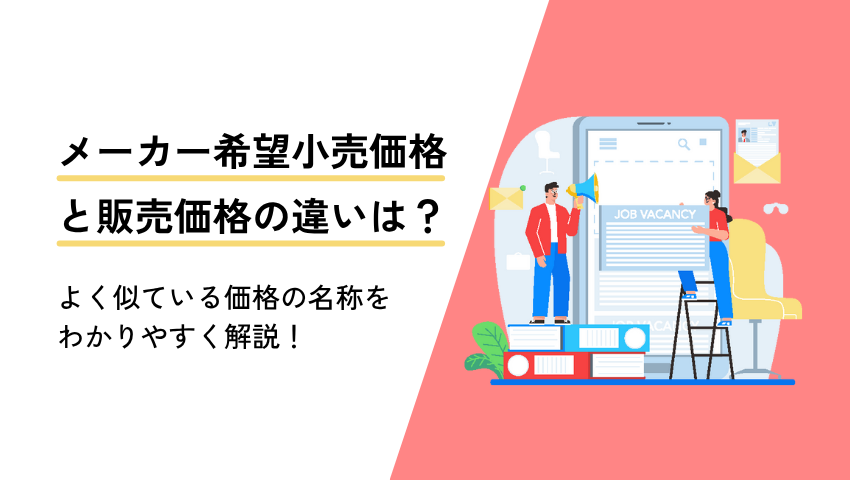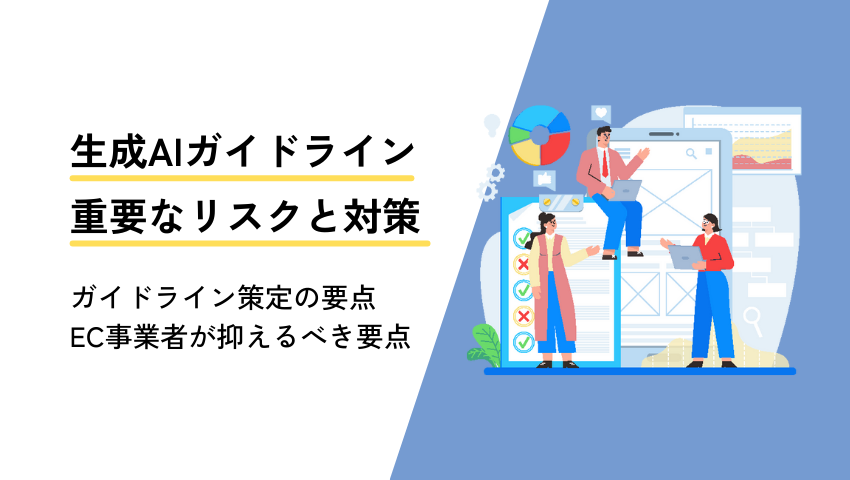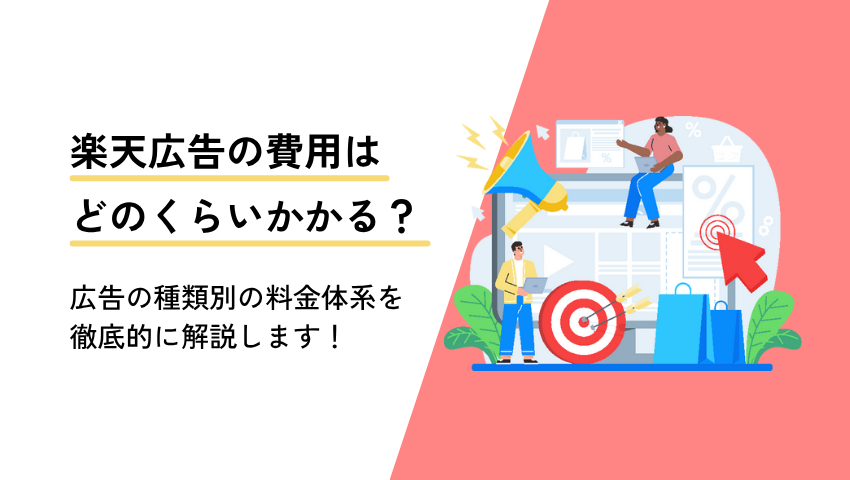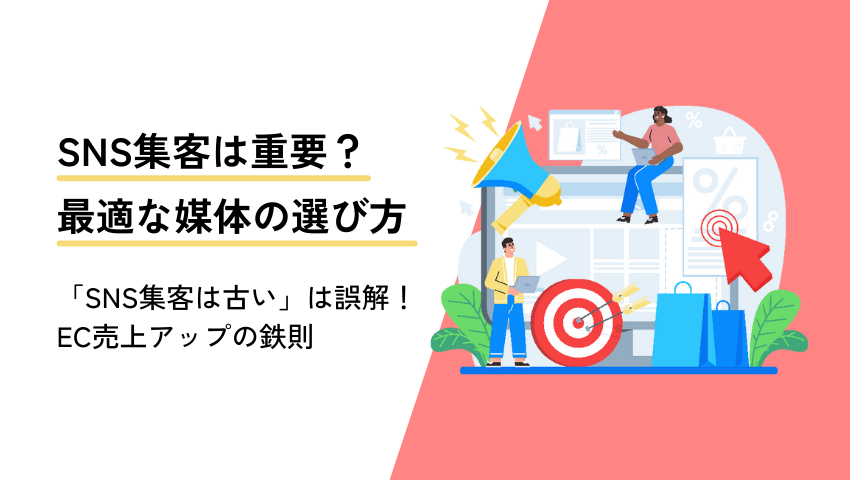キーワード一覧
キーワード検索
索引検索
あ行
-
エンゲージメント
「エンゲージメント」は日本語で「愛着」や「絆」と訳され、企業やブランドと顧客との深いつながりを指します。
Webマーケティングでは、SNS投稿への「いいね!」やコメント、シェアといったユーザーの自発的な反応の度合いを示す指標として用いられます。 数値が高いほど顧客の関心が高いことを意味し、ブランドへの忠誠心やロイヤルティを測る上で重要なものさしとなります。 -
エフェクチュエーション
「エフェクチュエーション」は、優れた起業家に共通する意思決定の理論です。
目的から逆算して手段を探す(コーゼーション)のとは対照的に、手元にある資源(手段)から何ができるかを発想して目的を見出します。 料理に例えるなら、レシピ通りに作るのではなく、冷蔵庫にある食材で何を作るか考えるのに似ています。未来が不確実な新規事業創出などで用いられる思考法です。 成功を収めてきた起業家に見られる、従来とは異なる思考プロセスや行動のパターンを体系化した意思決定理論で、バージニア大学ビジネススクールのサラス・サラスバシー教授が著書『エフェクチュエーション:市場創造の実効理論』の中で2008年に提唱しました。
現代は「不確実性の時代」ともいわれ、あらかじめ市場を的確に調査して把握したうえで、事業立案を行うことは困難になっています。これまでのビジネスでは、「目標」を決め、それに対して「計画」を立てて実行する「コーゼーション」という手法が主流とされてきました。これは予測可能な時代にこそ有効な考え方ですが、計画実施中に状況が変わることに対し、有効に作用しないこともあります。 -
エスノグラフィ調査
「エスノグラフィ調査」は「行動観察調査」とも呼ばれる定性調査の手法です。
対象者の普段の生活環境に入り込み、製品やサービスが実際にどのように利用されているかを深く観察します。 インタビューでは現れにくい無意識の行動や、本人も気づいていない課題を発見できるのが特徴です。顧客への深い共感が、新たな商品開発やサービス改善のヒントに繋がります。 -
エクスペリエンス
「エクスペリエンス」は日本語で「体験」「経験」を意味し、ビジネスにおいては顧客が商品やサービスを通じて得る総合的な体験価値を指します。
先に解説したUX(ユーザー体験)やCX(顧客体験)なども、このエクスペリエンスという考え方が根底にあります。単なる「モノ」の消費ではなく、満足感や感動といった「コト」の提供を重視する、現代マーケティングの重要なキーワードです。 -
インプレッション
「インプレッション」は、WebサイトやSNS上で広告などのコンテンツが表示された回数を示す指標です。
ユーザーがクリックしたか否かに関わらず、コンテンツが1回表示されると「1インプレッション」と数えられます。Web広告の効果測定において最も基本的な単位であり、「CPM(インプレッション単価)」などの関連指標の基礎となります。広告がどれだけ露出したかを示す、いわば「露出量」です。 -
インサイドセールス
「インサイドセールス」は、電話やWeb会議ツールなどを用いて遠隔で行う内勤型の営業手法です。
顧客を直接訪問するフィールドセールスとは対照的なスタイルを指します。 主に、マーケティング部門が集めた見込み客との関係を深め、購買意欲を高めてから営業担当者へ引き継ぐ「橋渡し」の役割を担い、営業活動全体の効率化に貢献します。 -
イベント
WebサイトやECにおける「イベント」とは、ユーザーがサイト上で行う特定の行動を指します。
例えば「商品の購入ボタンをクリックした」「動画を再生した」「資料をダウンロードした」といった一つひとつの操作がこれにあたります。これらの行動データを計測・分析することで、ユーザーの動向を深く理解し、サイト改善やコンバージョン率向上のための重要な手がかりを得ることができます。アクセス解析の基本となる概念です。 -
イーコマースモデル
「イーコマースモデル」は、インターネット上の商取引(電子商取引)のビジネスモデルを分類したものです。
取引の主体によってBtoC(企業対個人)、BtoB(企業間)、CtoC(個人間)などに大別されます。 例えば一般的なECサイトはBtoC、フリマアプリはCtoCにあたります。「誰に何を売るか」という事業の根幹を定義する、基本的な枠組みです。 -
アイトラッキング
「アイトラッキング」は、人間の視線の動きを追跡・分析する調査手法で、「視線追跡」とも呼ばれます。
ユーザーがWebサイトや広告のどこを、どの順番で、どれくらいの時間見ているかを専門の機器で計測します。 その結果はヒートマップなどで可視化され、「本当に注目されている箇所」を客観的に把握できます。Webデザインの改善や広告効果の検証に活用される、ユーザーの無意識を解明する技術です。 -
STP分析
「STP分析」は、効果的なマーケティング戦略を立案するためのフレームワークです。市場を細分化し(Segmentation)、狙うべき市場を定め(Targeting)、自社の立ち位置を明確にする(Positioning)という3段階の頭文字を取っています。 全方位的なアプローチを避け、自社の強みが最も活かせる顧客に集中することで、マーケティング活動の成果を最大化することを目的とします。1970年代から1980年代にかけて、アメリカの経済学者フィリップ・コトラーにより提唱されました。 -
SSL
"Secure Sockets Layer"の略で、インターネット上の通信を暗号化する技術です。個人情報やクレジットカード番号などを第三者による盗聴や改ざんから守ります。 導入されたサイトはURLが「https」で始まり、現在は後継技術であるTLS(ティ エル エス)Transport Layer Securityが主流ですが、総称としてSSL(エス エス エル)と呼ばれることが一般的です。顧客の信頼が不可欠なビジネスの、セキュリティの根幹をなす技術と言えます。 -
SEOチェキ!
「SEOチェキ!」は、無料で利用できるWebサイトの簡易SEO分析ツールです。
調査したいサイトのURLを入力するだけで、そのページの内部・外部リンク数やキーワード出現頻度といった基本的なSEO状況をすぐに確認できます。 専門的なツールと比べて手軽なため、自社サイトの基本的な健康診断や、競合の簡単な調査に広く活用されています。 <解析の視点>
検索エンジンにおける検索順位は、そのキーワードに対する消費者の関心の高さと比例します。単にSEOで短期的に順位を上げられたとしても、ユーザーの期待と異なった内容だった場合は見過ごされてしまい、検索結果の上位を維持することは難しくなります。 <ツールの使い方>
ツールに、対象ウェブサイトのURLと調査したい検索ワードを入力します。結果表示に若干時間がかかるケースがあります。ツールによっては、順位を定期的に取得するものもあります。
社名や製品名などの指名ワードで獲得できるのは主に顕在層であり、「一般ワード」で獲得できるのは潜在層のユーザーです。認知を広げたい場合や新規の顧客を開拓したい場合は、一般ワードの検索順位にフォーカスしましょう。 -
SEO
"Search Engine Optimization"の略で、日本語では「検索エンジン最適化」
と訳されます。Googleなどの検索エンジンで、自社サイトをより上位に表示させるための一連の施策を指します。 有料広告とは異なり、検索結果の自然な掲載順位での露出を高めるのが目的です。Webサイトを人通りの多い一等地に構えるための、重要なWebマーケティング手法の一つです。 -
ROI
"Return On Investment"の略で、日本語では「投資利益率」と訳されることがあります。
投じた費用に対して、どれだけの利益を生み出せたかを測るための指標です。この数値が高いほど、その投資が効率的で収益性が高いと判断できます。事業や施策の費用対効果を客観的に評価し、次の投資先を判断するための重要な意思決定材料となります。
ROI (%) = (利益 - 投資額) ÷ 投資額 × 100 -
RFM分析
顧客の購買行動を基にセグメント分けを行う分析手法です。
顧客を「Recency(最新購入日)」「Frequency(購入頻度)」「Monetary(購入金額)」という3つの指標で評価し、それぞれの顧客グループに最適なマーケティング施策を講じることで、顧客ロイヤルティの向上や売上アップを目指します。
「優良顧客」や「離反予備軍」などを可視化し、それぞれの顧客層に合わせた最適なアプローチを可能にします。顧客の価値を見極め、効果的なマーケティング施策を行うための羅針盤です。 -
OODAループ
「OODA(ウーダ)ループ」は、迅速な意思決定と行動を促すフレームワークです。
観察(Observe)→状況判断(Orient)→意思決定(Decide)→実行(Act)の頭文字を取ったもので、このサイクルを高速で回します。市場の変化が激しいWebマーケティングなどにおいて、計画に固執せず、現状に合わせて素早く最適解を導き出すために活用されます。スピードが求められる現代ビジネスにおける重要な思考法です。
アメリカ合衆国の戦闘機操縦士であり、航空戦術家でもあるジョン・ボイド氏が発明した意思決定方法で、彼はどんなに不利な状況からであっても、40秒あれば形勢を逆転できたということから「40秒ボイド」の異名を持っていました。そんな彼の強さの秘訣は、どんなに先の見えない状況の中でも迅速に意思決定を下し、迅速に行動に移す思考法にあったそうです。 軍を引退した後に人間の意思決定に関する研究に没頭し、その研究の末に作り上げたのがoodaループです。 -
OMO
"Online Merges with Offline"の略で、日本語では「オンラインとオフラインの融合」と訳されることがあります。
ECサイトなどのオンラインと実店舗のオフラインの垣根をなくし、一貫した顧客体験を提供するマーケティングの考え方です。顧客データや購買体験を統合し、両チャネルを自由に行き来できるようなサービス設計を指します。顧客を中心とした新しいビジネスモデルの要となる概念です。 -
LTV
"Life Time Value"の略で、日本語では「顧客生涯価値」と訳されることがあります。
一人の顧客が、取引を開始してから終了するまでの間にもたらす利益の総額を示す指標です。顧客獲得コスト(CPA)を上回るLTVを確保することが、事業を成長させる上で不可欠とされます。短期的な売上ではなく、長期的な顧客との関係性を重視する経営の要となる考え方です。
LTV = 平均購入単価 × 平均購入回数 -
Internet Archive
「Internet Archive」(インターネットアーカイブ)は、過去のWebサイトやデジタル情報を収集・保存している非営利団体の名称です。
特に「Wayback Machine」という機能が有名で、指定したURLの過去の状態を閲覧できます。競合他社のWebサイトが過去にどのようなデザインやメッセージを発信していたかを調査する際に重宝します。インターネット上の膨大な記録を保管する、巨大な図書館のような存在です。
URL:https://archive.org/ -
HTML
"HyperText Markup Language"の略で、Webページの土台となる構造を定義する言語です。
以前解説したCSSがサイトの「デザイン」を担当するのに対し、HTMLはテキストや画像といった「コンテンツ」の骨格を組み立てる役割を担います。検索エンジンもこのHTML構造を読み取ってページ内容を理解するため、SEO(検索エンジン最適化)の観点からも極めて重要な要素です。マークアップ言語とは
サイトのページを構成する、テキストに目印をつけたり、レイアウトの構造をコンピューターに認識させるための言語です。
コンピューターは、テキストをそのまま渡しても、タイトルは何で、どこが見出しで、どこまでが本文の段落なのかを理解することができない為、タイトル<title>・見出し<h1>・段落<br>などの目印<タグ>を付けることで、コンピューターにテキストの意味を伝えることができます。
ちなみに、マークアップ言語は、HTMLのほかにも、XML・XHTML・SGMLなどがあります。World Wide Web(ワールドワイドウェブ)の主な構成要素
・HTML:Hypertext Markup Language(エイチ ティ エム エル)
ウェブページに必要なハイパーテキストを実現するためのマークアップ言語
・HTTP:Hypertext Transfer Protocol(エイチ ティ ティ ピー)
パソコンやスマートフォンなどの異なるデバイス同士が通信を行うためハイパーテキストを送受信するのに使われる通信プロトコル
・URL:Uniform Resource Locator(ユー アール エル)
インターネット上の特定のファイルの場所を示す書式
形式→ [プロトコル名] :// [ドメイン名] / [ディレクトリ名] / [ファイル名]WEBブラウザとは
「browse(ブラウズ):拾い読み」という言葉が語源。
インターネットを介してWeb・ECサイトなどを、パソコンやスマートフォンで閲覧するためのソフトウェアのことです。
<主なWEBブラウザ>
Chrome(Google社)
Edge(Microsoft社)
Safari(Apple社)
Firefox(Mozilla社) -
ACOS
"Advertising Cost of Sales"の略で、日本語では「売上高広告費比率」と訳されることがあります。
主にAmazon広告などで利用され、広告経由の売上に対して広告費がどれくらいの割合を占めるかを示す指標です。この数値が低いほど、広告の費用対効果が高く、収益性が高いと判断できます。広告キャンペーンのパフォーマンスを測るための、いわば「健康診断」のような役割を果たします。
ACOS (%) = 広告費 ÷ 広告経由の売上 × 100 -
アルゴリズム
特定の問題を解決するための具体的な手順や計算方法、処理方法を指します。
簡単に言えば、「問題を解くためのレシピ」のようなもので、この手順に従えば誰でも確実に正しい答えにたどり着くことができます。もともと、大量のデータを高速で処理するために、コンピュータプログラムに組み込む計算手順や解決方法として使われてきました。
コンピュータが大量の単純な計算をこなす際、アルゴリズムを少し変更するだけで処理時間が大幅に短縮されることがあるため、効率化の観点から非常に注目されています。
アルゴリズムを利用する事で、どんな複雑な問題でも、最小限の手順で最適な答えを導き出すための設計図であり、特にコンピュータ処理の効率化においてその価値を発揮します。 -
ASP
アプリケーションサービスプロバイダー(Application Service Provider)の略で、インターネット経由でソフトウェアやサービスを提供する事業者、またはその仕組み自体を指します。
ユーザーは自分のコンピューターにソフトウェアをインストールする必要がなく、ウェブブラウザなどを通してサービスを利用できます。例えば、ウェブメールやクラウドストレージ、SNSなども広義のASPに含まれます。特にECサイトの分野では、ウェブページの作成、ショッピングカート、受発注管理など、ECサイト運営に必要な機能を一式で提供するサービスを「ASPカート」や「ASP型EC」と呼ぶことがあります。 -
運営代行
企業に代わり、ECサイトやWebサイトの日常的な運営業務を専門業者が請け負うサービスのことです。
商品ページの作成・更新、受発注管理、顧客対応、広告運用、アクセス解析といった実務全般、あるいはその一部を外部委託します。社内に専門知識を持つ人材やリソースが不足している場合でも、プロの知見を活用してサイトの成果を最大化させることを目的として利用される経営手法の一つです。