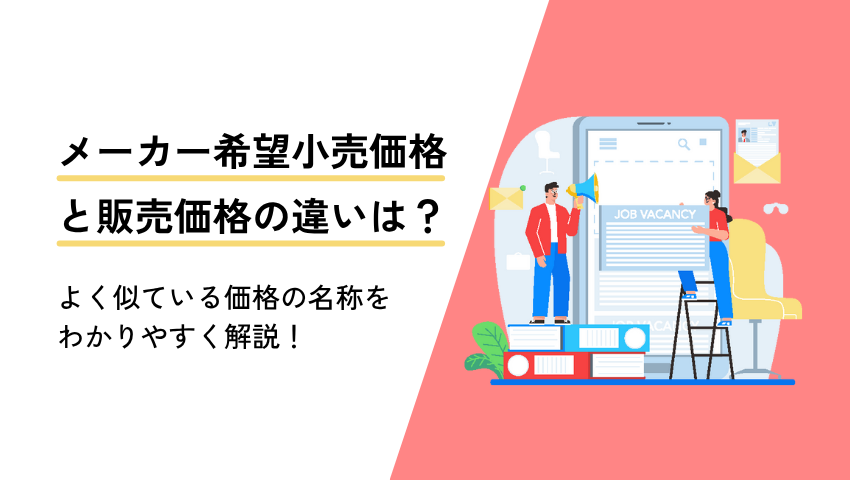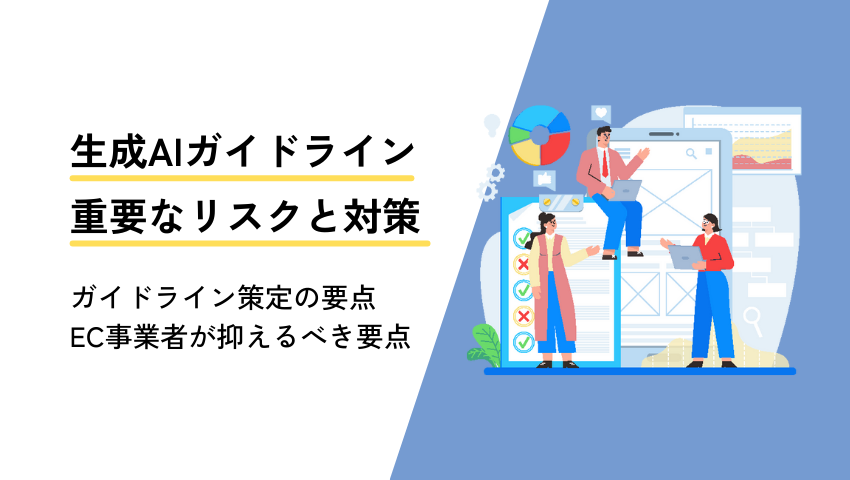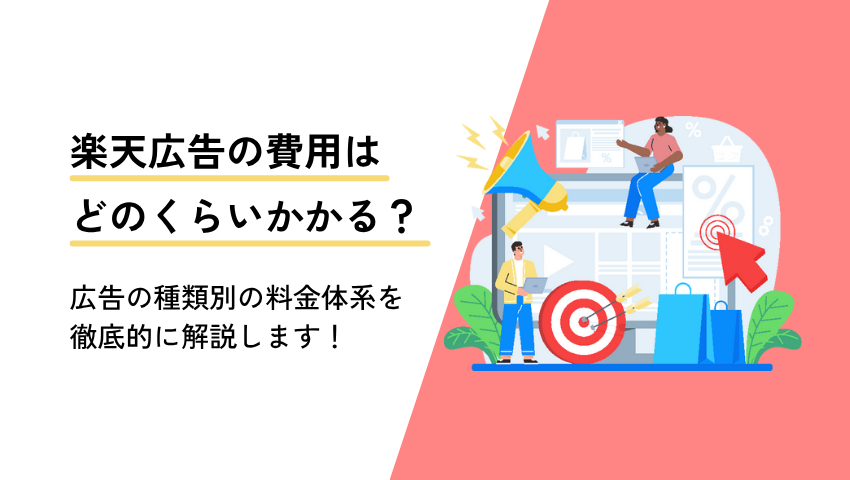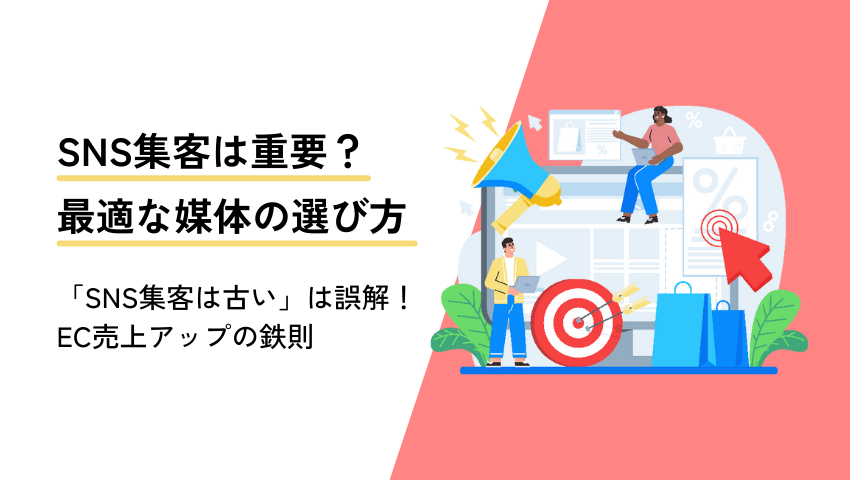- #コラム
なぜ?UGCが重要なのか。サイト運営担当者が意識すべきユーザーの声の重要性。
21
公開日
/
更新日

今日のWEB・ECサイトの運営において「ユーザーの声」は、単なる意見以上の価値を持つようになりました。レビューやUGCUGC
"User Generated Contenの略で、日本語では「ユーザー生成コンテンツ」と訳されます。企業ではなく、一般のユーザーによって...もっとみる(User Generated Content:ユーザー生成コンテンツ)といった形で発信されるユーザーの声は、消費者の購買行動に大きな影響を与え、事業の成長を左右する重要な要素となっています。サイト運営担当者は、その重要性を深く理解し、適切な対応を意識する必要があります。この記事では、サイト運営担当者が意識すべきユーザーの声(レビュー・UGC)の重要性についてまとめました。
目次
ユーザーボイス、レビュー、UGCの違い
- ユーザーボイス
商品やサービスを利用したユーザーが、実際の使用感や満足度について発信した声の総称を指します。これには、アンケートの回答、レビュー投稿、SNSでのコメント、サポート窓口への問い合わせ内容などが含まれます。ユーザーボイスの最大の特徴は、事業者側が想定していなかった視点や、ユーザーの率直な本音が含まれている点にあります。 - レビュー
ユーザーボイスの一種であり、特にECサイトなどで商品やサービスに対するユーザーの評価や感想を指すことが一般的です。多くの場合、星評価(★)とテキストによる口コミで構成されています。 - UGC(User Generated Content:ユーザー生成コンテンツ)
ユーザーが自主的に作成・発信するコンテンツ全般を指し、SNS投稿、口コミ、レビュー、動画、画像など多岐にわたります。企業が発信する公式コンテンツとは異なり、ユーザーの実体験や意見が反映されたリアルな情報が特徴で、消費者の共感を得やすく、口コミのように自然に拡散される傾向があります。
サイト運営においては、これらユーザーボイス、レビュー、UGCを「ユーザーの声」として統合的に捉え、その収集、管理、活用を進める視点が不可欠です。
なぜ今、ユーザーの声がサイト運営の成功に不可欠なのか。
- 消費者信頼の変化
今までのように、テレビCMやデジタル媒体による事業者が主体の広告は、「売り込み」と認識され、消費者に信用されにくくなっています。過去の調査では、SNSを日常的に利用する若年層の約7割が「広告を出稿する事業やブランドに対して好感度が下がったことがある」と回答しており、「過剰な表現」「広告の多さ」「信頼性の低さ」をその理由として挙げています。
事業者が発信する情報が、「都合の良い情報」として消費者に受け取られがちで、このギャップを埋める存在として、実際に商品やサービスを使用したユーザーの「リアルな声」が求められるようになりました。 - SNSの影響力
令和6年の消費者白書(消費者庁|https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/)では、商品やサービスを検討する際の情報源として、「家族・友人・知人」の意見が最も高く約4割、次いで「インターネット記事やブログ」が約3割を占めています。特に15~29歳の若年層では、「SNS」が最も高い約6割を示しており、事業者が発信する広告よりもユーザーのリアルな意見を信用する傾向が顕著で、消費者行動の意思決定において、第三者の客観的な意見が重視されていることを意味します。 - 購買行動における重要性
平成28年の情報通信白書(総務省|https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/h28.html)によると、20~40代の約8割、その他の年代でも7割近くが商品レビューを参考にしていると回答しています。さらに、レビューを読んだことで購入を決定した経験がある人は全年代で8割以上にも上ります。特に女性を対象とした調査では、約9割が商品レビューを「必ず見る」「よく見る」「見るときと見ないときが半々」と回答しており、レビューが購買行動に深く組み込まれていることが分かります。
こういった状況の中では、今までのような事業者側からの情報発信だけでは不十分で、ユーザーが自ら生成・発信するコンテンツ(UGC、レビュー)を戦略的に取り込み、その信頼性を活用することが、消費者行動にマッチしたアプローチであることを示しています。特に、情報収集の主要なプラットフォームがSNSである若年層をターゲットとするサイトでは、単なるマーケティング手法の一つではなく、ブランドと顧客の関係性、ひいてはビジネスモデルそのものの変革を意味しています。SNSを起点としたUGC戦略を最優先で構築し、それをサイトに連携させることで、ターゲット層の購買行動に直接的にアプローチできるため、未来の顧客基盤を築く上での不可欠な投資となります。
「ユーザーの声」がもたらすインパクト
ユーザーの声は、サイト運営において多岐にわたる具体的なビジネスインパクトをもたらします。その効果は、売上向上から顧客満足度、さらにはサイトの技術的な側面であるSEOSEO
"Search Engine Optimization"の略で、日本語では「検索エンジン最適化」と訳されます。Googleなどの検索エンジ...もっとみるにまで及びます。
- 売上・CVR(コンバージョン率)の向上
商品レビューは、購入を検討している消費者にとって強力な後押しとなり、売上アップに直結します。また、レビューが「購入済み」のユーザーによって書かれたものであると明示することで、その信頼性が高まります 。レビューは、購入を検討している消費者の不安を払拭し、購入への信頼感を醸成する役割を果たします。
サイト運営者は、単にレビューを集めるだけでなく、「いかに早く、信頼性の高いレビューを、適切な形で表示するか」に注力することで、コンバージョン率の向上が期待できます。 - 顧客エンゲージメントとブランド信頼の構築
「ユーザーの声」に耳を傾け、それに対応することは、顧客のエンゲージメントを深め、ブランドへの信頼を構築する上で不可欠です。顧客の不満や不安に早期に対応できるようになることで、「声を聞いてくれた」「改善してくれた」という実感が生まれ、企業への信頼や満足度が高まります。
また、良いレビューばかりが並ぶサイトは、消費者に偽のレビューではないかと疑われる可能性がありますので、サイトの透明性や正直さを示すためにも、ネガティブなレビューを恐れて、隠ぺいしたり、無視したりするのではなく、「戦略的に活用すべき資産」と捉えて、公開し真摯に対応することで、顧客との対話を深め、ブランドの信頼性を高めることができ、しいては顧客満足度だけでなく、結果的にCVRやLTVLTV
"Life Time Value"の略で、日本語では「顧客生涯価値」と訳されることがあります。一人の顧客が、取引を開始してから終了するまで...もっとみるの向上にも寄与する重要な戦略となります。
- SEO効果とオーガニック集客の最大化
レビューは、ユーザーが生成する良質なコンテンツであり、SEOSEO
"Search Engine Optimization"の略で、日本語では「検索エンジン最適化」と訳されます。Googleなどの検索エンジ...もっとみる(検索エンジン最適化)対策にもつながります。レビューが増えるほど、サイトの情報量が増加し、検索結果の上位表示につながる可能性が高まり、事業者が想定していなかったニッチなキーワードでも、ユーザーの投稿を通じて検索流入が増えるケースもあり、検索意図に合致したコンテンツが自然に生成されやすくなるという利点もあります。
- 商品・サービスの品質改善とイノベーションの源泉
「ユーザーの声」は、単なるマーケティングツールに留まらず、商品やサービスの品質改善、さらには新規事業のヒントとなる貴重な情報源です。事業者が想定していた使い方と顧客の実際の使い方とのズレを埋める具体的なヒントとなり、社内だけでは気づけなかった改善点が明らかになり、ユーザーの投稿を分析することで、想定していなかった商品ニーズや新しいターゲット層の発見、新商品開発のヒントにつながることもあります。 - 返品率の低減とLTV(客生涯価値)の向上
レビューがあることで、サイト訪問者はより詳細な情報に基づき商品を購入できるため、結果として返品を減らすことにつながります。レビューは商品理解を促進し、購入後のギャップを減らすことで、継続率の高いユーザーを獲得できるため、顧客生涯価値(LTV)の向上にも寄与します。
サイト運営担当者が意識すべき「ユーザーの声」の収集・管理・活用
「ユーザーの声」の重要性を理解した上で、次に意識すべきは、その効果的な収集、管理、そして活用方法です。適切な戦略とツールを導入することで、「ユーザーの声」のビジネスインパクトを最大化できます。
効果的なユーザーの声の収集方法
ユーザーの声を集めるには、複数のアプローチを組み合わせることが効果的で、最も一般的なのは、レビューリクエストメールの最適化です。
商品購入後やサービス利用後、顧客が商品を受け取った頃合いを見計らってレビュー記入を依頼するメールを送ることで、投稿を促進できます。この際、ポイントプレゼント、送料無料クーポン、画像付きレビューへの追加ポイント、レビュー大賞といったインセンティブを設けることは、投稿意欲を大きく高めます。
次に、アンケートとモニター活用も有効な手段です。アンケートは短時間で多くの声を集めやすく、コストも抑えられます。シンプルな設問に自由記述を組み合わせることで、傾向と具体的な改善点の両方を把握できます。また、モニターを募集して一定期間商品やサービスを試してもらい、体験を通じた声をヒアリングする方法は、実際の利用シーンに近い環境で感想を得られ、新たな視点での気づきや長期的な改善ヒントにつながります。
さらに、UGCの収集は、SNSに投稿された感想や写真には、ユーザーの本音や生活に根ざした使い方が数多く詰まっています。ハッシュタグキャンペーン、コンテスト、プレゼント企画などを通じて、ユーザーに自然な形で投稿を促すことができます 。商品名やブランド名でSNSを検索することも、思いがけない視点や実際の使用シーンを発見する有効な手段です。
また、新商品リリース直後からレビューの効果を最大化するためには、リリース前のレビュー収集も戦略的に検討すべきです。事前にメルマガなどを活用してレビューを収集しておくことで、サイト公開時からレビューが表示されている状態を作り出すことが可能になります 。
最後に、投稿フォームのUI改善は、レビュー獲得率に直結します。スマートフォンの利用率が高いことを考慮し、タップしやすいパーツ、ラベル配置、縦並び入力欄、プルダウン、分かりやすいエラーメッセージなど、モバイルに最適化されたフォームが不可欠です 。レビュー一覧、商品詳細ページのファーストビュー、マイページの購入履歴、ポップアップ表示など、投稿フォームへの複数の動線を設けることも重要です 。特に、ログイン不要でレビュー投稿を可能にすることは、ユーザーの心理的ハードルを下げ、レビュー投稿率を引き上げる可能性を秘めています 。
ユーザーは多忙であり、レビュー投稿には少なからず手間がかかります。ログインの必要性や複雑なフォームは、投稿率を低下させる要因となります。一方で、購入後の適切なタイミングでのリクエスト、ポイント付与やクーポンなどのインセンティブ、そして画像投稿への追加報酬は、ユーザーにとっての「価値」を高め、投稿への動機付けとなります。さらに、LINEのような日常的に利用するプラットフォームでのリクエストは、ユーザーの心理的ハードルを下げ、獲得率を劇的に向上させる効果が期待できます。
信頼性を高めるユーザーの声の管理と表示
収集したユーザーの声を最大限に活用するためには、その管理と表示方法が重要です。
まず、「購入済み」のユーザーによって書かれたものであると明示することは、レビューの信頼性を高める上で不可欠です。購入者が書いたレビューであることを明示することで、消費者はその内容をより信用し、CVRの向上にもつながります。
新着レビューの活用も重要です。トップページなど目立つ場所に新着レビューを表示することで、「商品レビューを積極的に収集していること」を認知させ、サイトの更新性をアピールできます 。さらに、事業者からの返信によるコミュニケーションは、顧客エンゲージメントを深めます。ユーザーのレビューに対し、事業者側が真摯に返信することで、ユーザーとの対話が生まれ、信頼性を一層向上させることができます。
適切な質問項目でUX向上を図ることも重要です。品質・価格、肌質・肌タイプ(コスメ・美容系)、身長・体重・購入サイズ(アパレル)など、商品の特性に合わせた質問項目を設定することで、ユーザーが求める情報を得やすくなり、購入後のイメージ違いによる不満を減らし、ユーザーエクスペリエンス(UX)を向上させます。
最後に、収集したレビューデータは、単に表示するだけでなく、データ分析に基づく改善を行うべきです。どのUGCがどれくらい成果につながっているかを可視化し、その分析結果をもとに、より成果の高いUGCを優先的に表示するなど、継続的な改善を行うことが重要です。
ユーザーの声活用におけるリスクと対策
ユーザーの声の活用は多大なメリットをもたらしますが、同時にいくつかのリスクも存在します。サイト運営担当者は、これらのリスクを事前に認識し、適切な対策を講じる必要があります。
- 法令遵守の徹底
ユーザーの声を活用する上で、最も重要かつ基本的なのが法令遵守です。
著作権・肖像権への配慮: UGCの著作権は投稿者に帰属するため、企業がウェブサイトや広告で利用する際は、必ず事前に投稿者の許可を得る必要があります。また、投稿されたコンテンツに第三者の肖像(顔や個人が特定できる情報)が含まれる場合は、その人物の許可も不可欠です。無断で掲載すると、不信感を招くだけでなく、法的な問題に発展する可能性があります。 - 薬機法(旧薬事法)への対応
化粧品、健康食品、医薬品などの商品に関する口コミやレビューをサイトに掲載する際は、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に抵触しないよう、表現を慎重に確認する必要があります。ユーザーが投稿した内容であっても、企業がそれを「掲載」することで、広告と見なされ、効果効能を断定するような表現や、誇大な表現が薬機法違反となる可能性があります。専門のレビューツールの中には、薬機法対策のための文章修正機能を持つものもあります。 - ステルスマーケティング規制への理解
企業が報酬を支払って投稿を依頼した場合、その事実を消費者に明示しないと、ステルスマーケティング(通称「ステマ」)と見なされる可能性があります。2023年10月1日からは景品表示法の不当表示として規制対象となりました。「#PR」「#広告」といった表記を明確に表示し、消費者に誤解を与えない透明な配慮が求められます。 - ネガティブなユーザーの声への適切な対応
ネガティブなレビューやUGCは、サイト運営者にとって懸念材料となりがちですが、適切に対応することで信頼性を高める機会となります。 - 無視しない姿勢
ネガティブなレビューは、顧客の不満や改善点を直接的に示す貴重なフィードバックです。これを無視することは、顧客の不満を放置し、ブランドへの不信感を募らせる原因となります。 - 真摯な返信
誤解がある場合は事実を修正するコメントを、店舗側の非が明らかな場合は誠意ある謝罪コメントを公開することで、顧客との対話を深め、信頼を向上させることができます 。真摯な対応は、他のユーザーにも誠実な企業姿勢として評価されます。 - 不適切なレビューへの対処
事実と異なる情報、嫌がらせ、商品に関係のないレビューなど、不適切な内容は公開を制限したり、個別に対応したりする必要があります。投稿フォーム上部に注意書きと問い合わせフォームへのリンクを設置することで、適切な問い合わせ先に誘導し、レビュー欄の健全性を保つ工夫も有効です。 - 自作自演レビューの防止
企業が自作自演で高評価レビューを投稿したり、報酬を支払って高評価レビューを書かせたりする行為は、消費者の信頼を著しく損ない、ブランドイメージに深刻なダメージを与えるため、厳に慎むべきです。 - データ偏りの防止
熱心なファンの意見だけを拾ったり、SNSの一部だけを見て判断したりすると、実態と異なる評価になる可能性があります。幅広い層からバランスよく声を集めることで、データが偏るリスクを避け、より正確な顧客ニーズを把握できます。
「ユーザーの声」の最大の価値は「信頼性」にあります。この信頼性を損なう行為(無許可掲載、ステマ、自作自演レビュー)は、短期的な利益追求に見えても、長期的にはブランド価値を毀損し、消費者からの信用を失墜させることにつながります。特に、薬機法のような法規制の遵守は、単なる法的義務ではなく、事業者としての「誠実性」を示す基盤となります。ネガティブレビューへの真摯な対応も、完璧さではなく「正直さ」を消費者に伝え、かえって信頼を深める機会となります。
運用コストと継続的な見直しの重要性
- 運用体制の検討
1件1件のレビュー承認作業や返信には手間がかかるため、運用コストが発生します。自動公開機能の利用や、適切な運用体制(担当者の配置、外部ツールの導入など)を検討し、効率的な運用を目指す必要があります。 - 定期的な収集と見直し
「ユーザーの声」は集めた瞬間がゴールではありません。商品やサービスが変われば、ユーザーの声も変化するため、定期的に新しい声を拾い、これまでの傾向と照らし合わせながら見直すことが不可欠です。
ユーザーの声は、一度集めて終わりではなく、商品やサービスの変化、市場トレンドの移り変わりと共に、その内容も常に変化する「生きたデータ」です。このデータ資産を最大限に活用するためには、定期的な収集、偏りのない分析、そしてその結果に基づいた継続的な改善が不可欠となります。運用コストは発生するものの、これは単なる費用ではなく、CVR向上、返品率低減、LTV向上、そして新商品開発といった多岐にわたるビジネスインパクトを生み出すための「戦略的な投資」と捉えるべきです。この継続的な投資によって、サイトは常に進化し、顧客ニーズに合致した最適な体験を提供し続けることができます。